「あり得た(る)かもしれないその歴史を聴き取ろうとし続けるある種の長い旅路、特に日本人やオランダ人、その他もろもろに関して/a long listening journey of a Possible thiStory especially of Japanese & Dutch & something more」
参考資料画像:Gedenkwaerdige gesantschappen der OostIndische Maetschappy in’t Vereenigde Nederland、1669
プロジェクトについて
本シリーズは、1669年にオランダ・アムステルダムで出版され、西洋社会に「日本」とそこにすむ人達、文化、歴史を初めて体系的に紹介した「モンタヌス日本誌*」という地理本に含まれる100枚以上の緻密な銅版画や456ページのテキストに描かれた想像に富んだ「日本」を出発点としする。
それらのイメージが生まれたプロセスや時代背景、異なる存在としての日本人を描きだすために誇張されたお辞儀などのしぐさ、また身体そのものを変態させる作画法によって描かれた人や偶像、また彼らが知り得ていた限りの「東洋」的な要素をマッシュアップしたような風貌をもつ人や風景などを「あり得た(る)かもしれない」とし引受け現代と関連付けて読み解くことからマージナルでマイナーな複数形の歴史群(histories)に耳をかたむけ、土地土地に残響する複雑なポリフォニーをすくい取る。
特に17世紀オランダ東インド会社時代、20世紀の第二次世界大戦期にオランダと日本が直接接していた土地としてバタヴィア(現在のジャカルタ)や、ゼーランディア(現在の台南・安平)、平戸などをリサーチ、取材した内容を題材に、様々なコラボレーター達と各チャプターを制作し「あり得た(る)かもしれない」歴史をコレクティブに再想像することを試みています。
*原題「Gedenkwaerdige Gezantschappen der Oost-Indische Maatschappy in ’t Vereenigde Nederland, aan de Kaisaren van Japan」(アルノルドス・モンタヌス著、ヤコブ・ファン・メイウス編、1669、アムステルダム):「モンタヌス日本誌」に含まれる17世紀オランダ産の「日本」のイメージは誤解や先入観を含み、結果的には後にステレオタイプを生み出すことなる一方で、文字記録・伝聞を元に発揮されたコレクティブな想像の産物として見るならば、特異な跳躍が感じられ、単一的になりがちな国家や「〜人」という枠組みを脱却しており魅力的ですらある。
*「東インド会社遣日使」等、他の名称で呼ばれることもある。
レクチャー・パフォーマンス・パーティー

2018年2月23日、「第10回恵比寿映像祭「インヴィジブル」」、ガーデンルーム、東京
出演:mamoru(MCなど)、河合真人(声明)、So Oishi(DJ)、鍾繼儀(打楽器、スオナ)
言語:日本語と英語、一部でインドネシア語、逐次字幕あり
映像ドキュメント、日本語オーディエンス版、撮影・編集:Higuchi Yuki
https://youtu.be/LhrcVoHwPVI
トレーラー(約5分)
https://youtu.be/OAIPQ-C_lOQ
「モンタヌス日本誌」のイラスト、断章的な幾つかの映像、またミュージシャン達(ジャワ・ガムラン演奏家、パーカッショニスト、台湾伝統音楽家、DJ、僧侶)をフィーチャーしつつ展開されるポリフォニックなパフォーマンスは、レクチャーと絡み合いながらライブ時間上にアクティベイトされていく。パフォーマンス中に使用される言語は主に日本語でありつつも、英語に切り替わる部分があったり、時に日・英ではない言語が挟まれ、音楽がレイヤーされたり、ポリフォニー又はカコフォニーの様相を生みだす。プロジェクションされる字幕テキストがパフォーマーの台詞を離れて独り歩きする場面など、テキストー声ー音による音楽的で詩的な拡がりを持たせ、パフォーマンスの後に設けられたアフターアワーズでDJが人々を踊りへと誘い、複数的な歴史・世界を体現することを目指す。
CHAPTERS
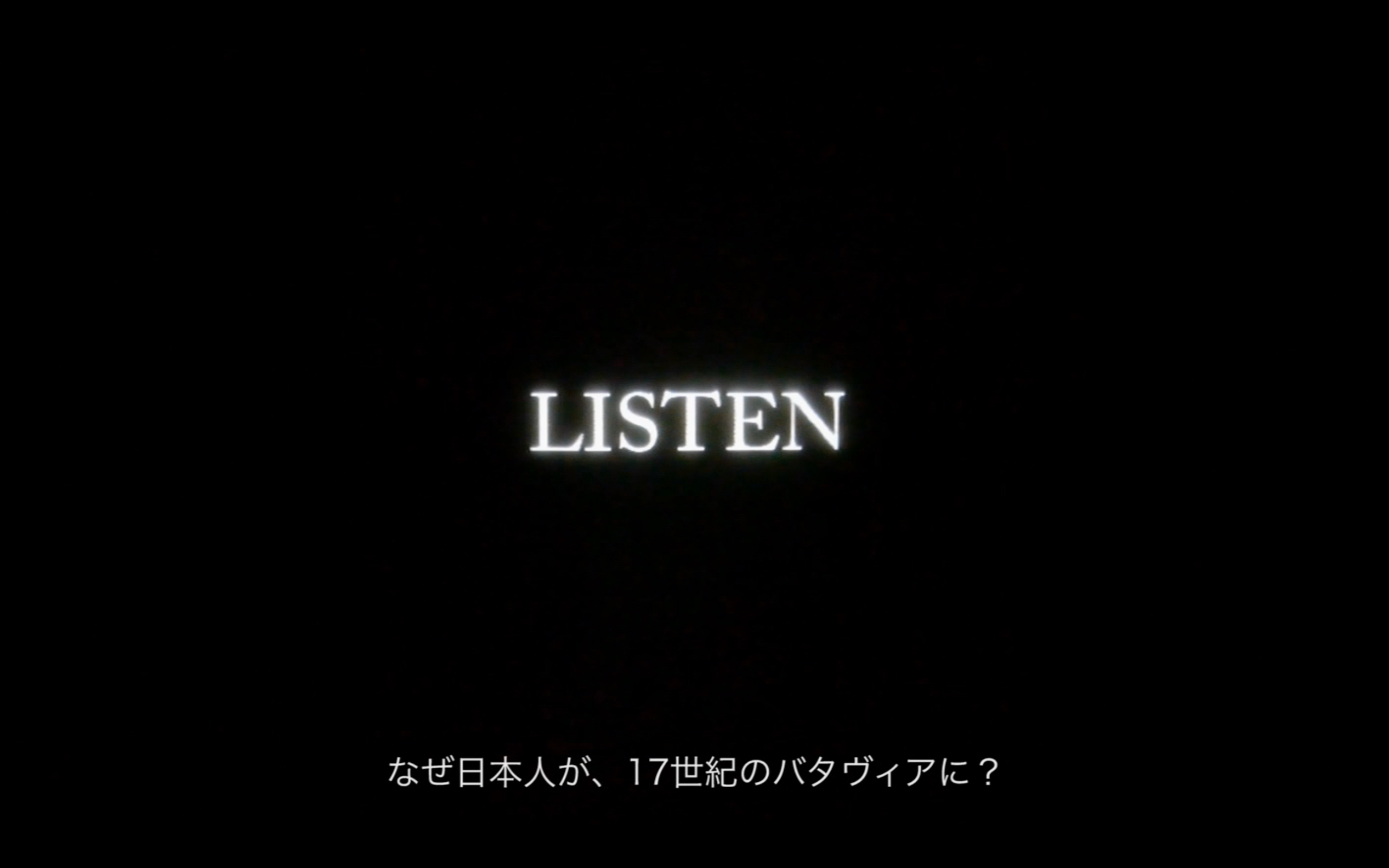
第一章 : this voice - a place - all that is resonating / この声・ある場所・残響するすべて
(シングルチャンネルフィルム、HD、ステレオ、9'34"、2016)
トレーラー: https://youtu.be/sYV5eODwXW0
第二章:Art of Japanese Bowing / (ジ)ヤパニーズのお辞儀
(ソロパフォーマンス、2チャンネルプロジェクション、音声エフェクト、言語:英語、約10分、2016)
https://youtu.be/VuQmsxKO-zE
1、2章続き日本語字幕付き(冒頭と最後一部なし): https://vimeo.com/194191015
1、2章続き字幕なし: https://vimeo.com/178537574
第三章:Further / 遠くへ
(シングルチャンネルフィルム、HD、ステレオ、10’10、2016)
トレーラー: https://youtu.be/EuaMOQ9393M
コラボレーター
ダンス:刈谷円香(Netherland Dans Theather所属)
カメラ:ソル・アーチャー

Photo: Ken Kato
第四章: outstretched / 伸ばした手
(シングルチャンネルフィルム、HD、サイレント、3'19"、ループ、2016)
トレーラー: https://vimeo.com/172730288
コラボレーター
カメラ:ソル・アーチャー

Photo: Ken Kato
第五章: becomings/投げ出された身体
(シングルチャンネル/プロジェクション、HD、8バリエーション
各3'17 ランダム再生、非シンクロステレオサウンド* 、32bit 192khz, 26'14" ループ再生)
*サウンドは以下の4トラックで構成
1: UpperSange 2017 ver.1 6'55"
2: UpperSange 2017 ver.2 6'40"
3: NamuamiDub (remix: So Oishi) 6'12"
4: Amidachyon (remix: So Oishi) 6'24"
トレーラー:https://youtu.be/cO_LuPO5Vfw
コラボレーター
声明:河合真人
ドラム:アルヴィン・サトゥルアニ
ガムラン楽器(ゴング、シトゥル):ヴェリー・ヘンドゥラモコ
リミックス:So Oishi
ビジュアル・リミックス・ヒュンテ・リー

第六章:Sebuah Tempat / セブア・テンパ
(シングルチャンネルフィルム、HD、 ステレオ、6'23"、 2017)
トレーラー:https://youtu.be/1cl_K6L15ik
コラボレーター
声、翻訳:Puput Sri Rezeki *ナレーションの原文は英語
ギター:Rangga Purnama Aji

第7章:Firando Tayouan Batavia / ヒラド タイハン ジャガタラ
(5 チャンネルヴィデオ・インスタレーション、HD、10'47"、2018)
インスタレーション・ビュー:
トレーラー:https://youtu.be/8lmNm-mGJks
コラボレーター
衣装:有本ゆみこ(SINA SUIEN)
出演、リサーチ: Mutia Amelia Febriana

第八章:Suspended on A Historic Bowing / とある歴史的なお辞儀に関する宙に浮いた想像
(ソロレクチャー・パフォーマンス/約15分、シングルチャンネルプロジェクション、ヘッドセット・マイク、Tシャツ、エッチング、フレーム、2017)
コラボレーター
インドネシア語版 翻訳、パフォーマンス: Forrest Wong *原版は英語
エッチング:Puput Sri Rezeki
コーディネート: 横内賢太郎
video documentation:
https://youtu.be/-RgDIy43CPI
*本章をご覧になるにあたり Chapter2 を事前にご覧になるか、その両方が含まれるレクチャーパフォーマンスをご覧になることをおすすめします。